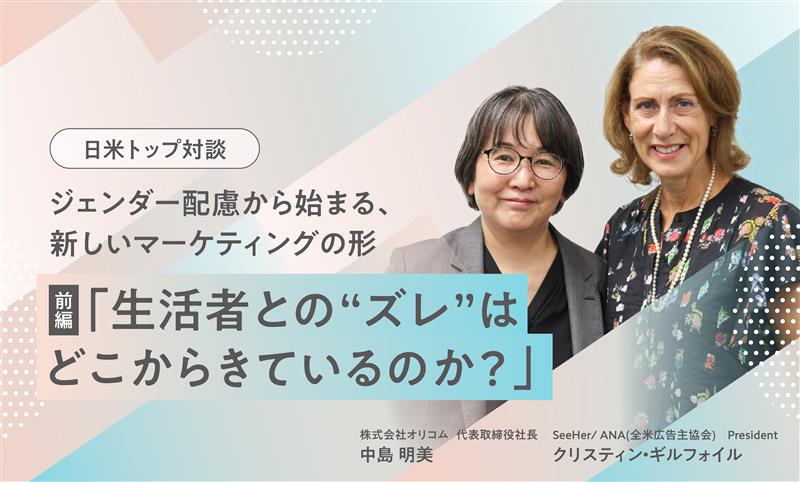近年、広告業界において“多様性”“DEI”という言葉をよく見かけるようになりました。なかでもジェンダーに関しては、一歩間違えると炎上につながりやすく、生活者の意識も高まっている領域です。
「そんなつもりじゃなかった」から生まれる生活者との“ズレ”はどこからきているのか、そして、マーケターやクリエイターはこの問題にどのようにして取り組めばいいのか?
本記事では、広告におけるジェンダーバイアス測定基準「GEM®」の発案元であるSeeHerのプレジデントのChristine Guilfoyle(クリスティン・ギルフォイル)氏と、日本で「GEM®」を推進する当社の代表取締役社長である中島明美氏が意見を交わします。
対談者
Christine Guilfoyle(クリスティン・ギルフォイル)
SeeHer/ ANA(全米広告主協会) President
Better Homes & Gardens、Martha Stewart Living、EveryDay with Rachael Ray、Shapeなど、アメリカで最も愛される女性向けライフスタイルブランドにおいて、マルチチャンネルメディアブランドのリード、移行、立ち上げ、成長に焦点を当てながら、戦略的リーダーシップを発揮。Meredith Corporationでは、Martha Stewart LivingとMartha Stewart WeddingsのSVP/グループパブリッシャーを務めた。
また、The Magnolia Journal と Allrecipes Magazine の立ち上げを主導し、Every Day with Rachael Ray、Eating Well、Shape の買収をリード。Womens Wear Daily誌への発行人として、日刊の業界紙から包括的なマルチチャネルのグローバルメディアブランドへ転換をする際の指揮を執った。
さらに、Every Day with Rachael Rayを立ち上げたチームを率い、Advertising Age、Adweek、MINからLaunch of the Year Awardを受賞。FOLIOは、2014年にクリスティンを「Top Women in Media」の初代リストに選出し、2016年にはMINのセールス殿堂入りを果たし、2017年にはFolioの名誉である「Top 100 Honoree」を受賞。クリスティンは、Cosmetic Executive Women (CEW)、She Runs It、New York Women in Communicationsの長年のメンバーとしても在籍する。また、マリスト大学生涯教育学部とニューヨーク大学夏季出版研究所の理事を務める。
中島 明美
株式会社オリコム 代表取締役社長
男女雇用機会均等法施行3年目の1988年、新卒で株式会社オリコムに入社、ストラテジックプランナーとして、主に消費財メーカーのマーケティング、コミュニケーションプランニングに関わる。2012年にコミュニケーションデザイン局長となり、2017年にデジタルソリューション局長を経て、同年、生活者理解に基づく「時×場×情」のソリューションを提供するべく、企画制作本部長に就任。創業100年を迎える広告会社の初の女性取締役となる。2023年代表取締役社長就任。AWA2023「Future is Female Awards」10人のファイナリストのひとり。
広告ビジネス、日米それぞれの事情。
中島:はじめに、広告会社におけるジェンダーバイアスについて話をしましょう。私は、日本で男女雇用機会均等法(1985年)が制定された3年後に新卒としてオリコムに入社しました。それまでは女性が男性と同じように大学を出て就職するというのが非常に難しかった時代です。そのため、広告会社でも大卒女性と言うだけで採用が無い会社もまだまだありました。私はたまたまオリコムに入社出来ましたが、あの時、ビジネスの世界においては、大卒女性はようやく開いた門戸の隙間を狙うような、その程度の扱いだったというのが個人的な記憶です。
クリスティン:それはひどいですね。信じられない話ですが、アメリカでも少し前までは、女性向けの商品に関わるクリエイティブ、メディア、戦略の現場に女性はほとんどいませんでした。女性に向けて売られ、女性に購入され、女性に必要とされる商品でさえ、すべて男性によって作られていたのです。今日においては進歩が見られるものの、依然としてクリエイティブ部門のトップの多くは男性であり、まだまだ課題は山積みです。
中島:そうなんですよね。日本でも広告ビジネスにおいては同様で、まだまだ女性が関わる領域は十分とは言えません。男性の目を通した解釈が多くなりがちで、女性のリアルを描いているとは言い難い場面もしばしば。固定観念に縛られていると思うことも少なからずあります。
クリスティン:男性の多くが過去の固定観念に固執している部分があるのだと思います。アメリカでは広告業界において「SeeHer」という活動があり、私たちは女性や少女をより現代的で、ありのままで、尊重に満ちた、偏見のない形で描くことで、広告やコンテンツを通して社会や文化を変えることができると信じています。しかし一方で、いまだにクリエイティブの表現にはステレオタイプ的な役割が残っている部分もあります。状況は改善されつつありますが、一進一退を繰り返している状況です。
変化をすることの、難しさ。
クリスティン:なぜ、一進一退を繰り返しているのか?それには2つの理由があります。ひとつは、権力を持つ男性たちが変化を望んでいないこと。そしてもうひとつは、ただでさえマーケターのやるべき領域が広いうえに、進化の早いテクノロジーや、コミュニティ(世代、人種、LGBTQなど)毎の対応に追われ、つい慣れている従来のやり方に頼ってしまうということです。
中島:「変化をする」というのは様々な恐怖が伴いますよね。
クリスティン:その通りです。しかしアメリカでは、若い世代(ミレニアル世代やZ世代、そして次に続くアルファ世代)が、ブランドに対して現代的であることや、社会的な意義を持つこと、また、より包括的かつインターセクショナルな方法でキャラクターや人物を描くことを求めています。一方で、私たちの世代は、ステレオタイプや偏見に慣れてしまっていて、ブランドがそうした描写をしても、つい許してしまうことがありますよね。ある意味では彼らを大目に見ているわけです。しかし、新しい世代はそうはいきません。彼らは別の選択をするでしょう。そのため、ブランドや企業は変わるべきか、それとも今までのコントロールを手放し、若い世代が望む形で語りかけるべきか、どちらを選択するかの決断を迫られています。
中島:ここで難しいのは、できるだけ多くの人の共感を得ながら変化を進めたい、とはいえ、過度に調和を求めすぎると変化のスピードが遅くなってしまう、このジレンマがついて回ることです。そして、その変化に対するスピード感を若い世代からは特にシビアに評価されていると感じています。 ジレンマに立ちすくんでいては彼らの声に応えられません。
クリスティン:そうですね。さらにアメリカの場合、ブランドや企業の選択を複雑にしているのが、様々な人種・宗教・民族などを包括した国家であるという点です。
そのため、『みんなに向けたメッセージ』から離れ、多様性や交差性(複数のアイデンティティが重なる視点)を広告制作の際に考慮することが多く、そこにも難しさがあるのですが、日本はいかがでしょうか?アメリカほど多様な人種・民族がいるわけではないため、そこまで複雑に考える必要はないのでしょうか?

中島:確かに日本はアメリカほど人種・民族の多様性は強くないですが、そのかわり「みんな」が先行してしまい、個々の違いに蓋をするような同調圧力が強いと思います。本当は違うのに、違うことを認めてもらえない、表面的な「みんな一緒」が正しい、という空気に流される。そして広告が、ともすれば「みんな一緒」がいいよねという空気を安易に強固にしてしまっているのが気がかりです。
分かりやすい記号から、離れる。
クリスティン:そういえば、日本でタクシーに乗車した際に見た広告では、女性が姉妹のようにそっくりで、みんな同じ人にも見えました。髪型も、体型もみんな同じで、そこに違いを感じられないような描き方です。
中島:タクシーサイネージではBtoB向けの商材がよく流れてきますが、その訴求方法として、しばしば若い女性に擬人化した広告表現が使われます。若くてかわいい、少し胸が大きいような女性ですね。こうしておけば収まりがいいだろう、決定権者であり利用者であるはずの男性にとって受け入れやすいだろう、というのが透けて見えます。本当にそうか、は別としてですが。
クリスティン:確かに、若くて可愛くて痩せていました(笑)。描き方の多様性という観点では、ユニリーバやP&G、マスターカードといった大手のグローバルブランドが良い動きをしていると思います。例えば、年齢や体型の異なる女性を描いたり、黒人や褐色の女性、同性カップルも登場させたりと、幅広い表現が見られますね。とはいえ、残念なことに依然として同じような女性しか描かない企業もたくさんあるのですが・・・。
中島:そうですよね。私はもっと様々な人が描かれていいと思います。例えば、厳しいおばさんや優しいおじさんでもいい。「若い女の子」一辺倒というのはつまらないし、なにより受け手に対する想像や視点が足りていないと感じます。
クリスティン:アメリカでも似たようなことは起きています。例えば検索画面で「Boss」と入力すると、その検索結果に表示される画像の多くはブリーフケースを持ったスーツ姿の男性で、多くは白人です。一方で「Bossy」(=ボスっぽい、偉そうな)と入力するとその検索結果には女性が出てきます。男性が「ボス的」と表現されることはありません。彼は「ボス」として表現されます。男性に対しては「攻撃的」と表現されず、「自己主張が強い」と表現されるでしょう。残念なことに、ネガティブな形容詞を入れると「女性」が、ポジティブな形容詞を入れると「白人男性」になることが多いんです。
また、アメリカでも、以前は一般的な市場とは、白人男性を対象としたマーケティングのことでした。女性でさえもマイノリティ・マーケティングであったのです、たとえそれが人口の50%であったとしても。その名残は今もありますよ。
中島:なるほど・・・。性別とイメージの結びつきを固定化してしまうのはよくないですね。そもそも、男性はこう、女性はこう、というのも決めつけかなと思います。ブリーフケースやスーツに縁が無い男性だっているし、自己主張が強い男性を煙たがる男性だっていますよね。なにが自分らしいのかは人それぞれ。女性だけではなく、男性に対する固定観念についても考える必要があると思います。

とはいえ、ここであえて逆のことを言いますね。ダイレクトマーケティングの世界だと特にそうだと思うのですが、アクションを起こさせる広告やコンテンツでは、分かりやすい記号を使う方が、ビジネス的には結果につながりやすいということにも触れておく必要があると思います。「誰向け」なのか、「何を売りたい」のか、を明快に伝えようとすれば、ある種のステレオタイプ化は避けられません。コストの問題もありますが、何より成果を求められる以上、アイキャッチとして分かりやすい記号を選択するのは必要なことで、結果的にステレオタイプをより強固なものとしてしまうことはあると思います。我々が目指しているのはその記号から離れることですが、ビジネス上のKPIをおろそかにしても良いとは思っていません。
クリスティン:その通りです。マーケターにはKPIが必要ですから、まさにそこがGEM®を立ち上げた理由の1つです。SeeHerでは過去4年間、GEM®と売上に相関があるかを検証してきました。その結果、GEM®スコアが110以上であれば売上が伸びるというデータを得ることができました。アメリカ国内に限定はされますが、今ではGEM®を用いてブランドの評判、購入意向、行動喚起など、ブランドに関わる指標の測定が可能になっています。このようなデータを見ていくことで、正しいアプローチを取ればビジネスの成長に繋がることが示せていると思います。
中島:日本ではいまだに「多様性」や「DEI」というと、組織の在り方や人権研修といったインナー向けの文脈で議論されていることが多いですが、これからは「マーケティング×DEI」というビジネス視点も必要になってくると考えています。そのことからも、GEM®と売上に相関があるというデータの存在は心強いですね。
>>【後編】「感情的な領域だからこそ、数字が活きる」 に続く
ジェンダーバイアス測定基準「GEM®」

ジェンダーバイアスの視点から、広告やコンテンツの表現を生活者がどう受け止めているかを測定する調査「GEM®(=Gender Equality Measure)」についてご紹介します。